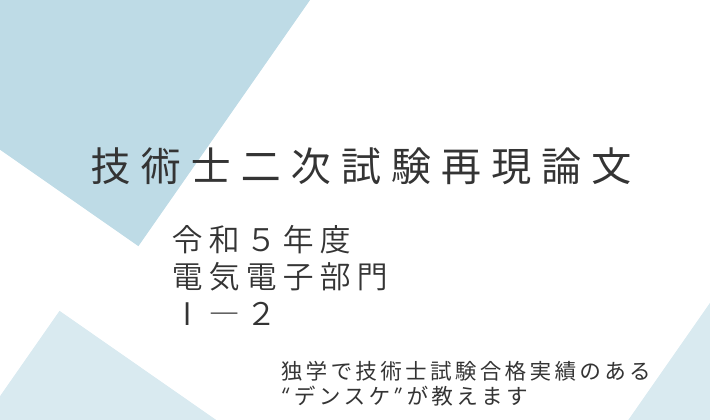こんにちわ、デンスケです!
令和6年度技術士第二次試験(電気電子部門)に独学で合格実績のある”デンスケ”が、”最新”の技術士試験の合格ノウハウを伝えたいと思います。
ブログに不慣れなので、まずは単純に、自分が試験で回答した論文の再現を公表してみます。拙い内容で、誤りも含まれると思いますが、ご容赦ください。
今回は、令和5年度 電気電子部門Ⅰ―2です。
合否通知では、B判定(得点率40%以上60%未満)となっていました。残念ながらこの時点で不合格確定でした。
問題
これからのモビリティ社会では、EV(Electric Vehicle)が重要な役割を果たすことが期待されているが、社会のインフラ技術に与える影響は大きいと思われる。EVが普及した社会におけるインフラ技術を考えるうえで鍵となるものは、根本的な課題解決の観点をどのようにとらえるかである。そのうえで、解決策と将来像についての道筋を示すことが求められる。これらを踏まえ、以下の設問に技術面で解答せよ。本問は、EVが普及した社会におけるインフラ技術に向けた考え方を問うものである。(政策などは含まない。)
(1)技術者としての立場で、EVが普及した社会におけるインフラ技術の根本的な課題を多面的にとらえ、重要と考える3つの観点を抽出して、それぞれの根本的な課題の内容を示せ。(*)
(*)解答の際には必ず観点を述べてから技術課題を示せ。
(2)前問(1)で抽出した技術課題のうち最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、これを最も重要とした理由を述べよ。その課題に対する電気電子分野関連における解決策を3つ、電気電子部門の専門技術用語を交えて示せ。
(3)前問(2)で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
(4)前問(2)で示した解決策の実施において、技術者としての倫理、社会の持続可能性を踏まえて必要な要件を題意に即して述べよ。
再現論文
1.EVが普及した社会におけるインフラ技術の課題
(1)安定運用の観点から(電力供給)
モビリティ部門のエネルギー消費量は多いことから、従来の化石燃料から電力に燃料を転換した場合、電力の供給力に懸念がある。また、電力需要変動だけでなく、再エネの出力変動にも対応する調整力を確保する必要がある。安定運用の観点から、電力の供給力、調整力の確保が課題となる。
(2)利便性の観点から(充電スポット)
モビリティは人間生活を支えるものであるため、EVの充電が支障になることは望ましくない。EVは、従来の化石燃料を利用した車に比べて、航続可能距離が短い、充電に時間がかかる、充電可能場所が現敵的であるという特徴がある。利便性の観点から、充電場所の拡充、急速充電機能の改良等のインフラ整備が課題となる。
(3)環境適合性の観点から
モビリティ部門はエネルギー消費量が多いことから、環境に与える影響に留意する必要がある。EVの充電に当たっては、可能な限り、CO2を出さない発電方法によって供給するべきである。また、EV生産や機器輸送、工場の建築等においても環境負荷リスクがある。環境適合性の観点から、サプラチェーン全体でのCO2削減をはじめとする環境負荷低減が課題となる。
2.電力供給の課題の解決策
課題(1)を解決しなければモビリティ社会が成り立たないこと、課題(1)を解決することで課題(2),(3)にも改善効果があることから、課題(1)を最重要課題とする。解決策を以下に示す。
(1)新たな電気料金プランの設定
電力供給面では、従来の負荷平準化の観点からだけではなく、再エネの発電状況等も加味して、最適なロードカーブとなるよう電力需要を誘導することが、安定供給、経済性、環境適合性において有効である。現在は、スマートメータの普及により、30分事の計量か可能であり、リアルタイムに近いレベルで需要実績の把握が可能になってきている。これを踏まえ、電気料金の時間帯の細分化、実需給状況を反映した料金設定となるプランを作ることで、需給運用の最適化を測る。
(2)EVの充電、放電制御
電気料金等の指標を元に、EVの充電を制御し、需給運用の最適化を行う。V2HやV2Gのように、EVに充電した電力を家庭や電力系統向けに流すことも行い、最適な需給運用を目指す。
(3)調整力としての活用
アグリゲータの取りまとめによってEVの充電、放電を上げDR、下げDRとして活用し、調整力として利用する。
3.新たに生じうるリスクと対応
(1)システム停止リスク
電気料金プランやEVの充電、放電制御を高度化した場合、システム停止時にEVが充電できないだけでなく、電力供給がままならなくなるリスクがある。対策として、システムの二重化、ファイアウォールやセキュリティソフト導入などのセキュリティ対策、ヒューマンエラー防止のための人材育成等があげられる。
(2)過制御リスク
電力の供給力に余裕のある時間帯にEVの充電を誘導した結果、返って供給力が不足するリスクがある。対策として、需給状況をリアルタイムで反映し、フィードバック制御を取り入れることが挙げられる。
4.技術者倫理、社会の持続可能性からの必要要件
技術者倫理については、教習の安全、健康、福利を最優先に考える。インフラの性能や品質より、コストや納期を優先してしまい、データや計算書の改ざん等の反倫理的行動をとることは絶対にあってはならない。このため、倫理教育の徹底に加え、改ざん等の不正が行われにくい業務の仕組み、システムの構築も有効である。
社会の持続可能性に関しては、地球環境や生態系を含む環境に与える影響を最小化する。エネルギー効率化やリデュース、リユース、リサイクルに代表される資源の有効活用も重要である。
以上
反省点
技術士二次試験 初挑戦の令和5年度は、設問ⅠがB評価となり、不合格となりました。
受験前、科目Ⅰは設問(4)で毎年ほぼ同じ内容の倫理に関する内容が問われるため、ここで確実に得点することで合格しやすいだろうと思っていました。逆に科目Ⅱの論説問題の方が、デンスケの業務経験的に難しいだろうと思っていました。結果は真逆でした。。。
設問(4)は、受験前に丸暗記していった文書を書いたのですが、おそらく、題意に即していない(これまでの回答内容とのつながりがない)ということで、得点がもらえていないような気がします。今回の再現論文の場合は、システム開発時に不正を行わない、システムのハード構築時に環境負荷を低減できるよう考慮する等を書ければよかったのかと思います。独学でやっていたため、NG判定を食らうまで回答内容とのつながりを全く意識できていませんでした。落ちるべくして落ちたようなものだと思っています。
反省点をもう1つ挙げるとすれば、解決策(1)新たな電気料金プランの設定 は、問題文の指示「政策などは含まない」に合致していないという判定で、得点につながらなかったのではないかと思います。多面的な観点を意識しすぎたあまり、問題文を意識できていませんでした。これも、事前に作戦を練っておくべき反省点でした。「新たな電気料金プランが導入可能となるシステムの開発」のように、語尾をシステムにするだけで、技術的な内容にシフトできたのではないかと反省しています。