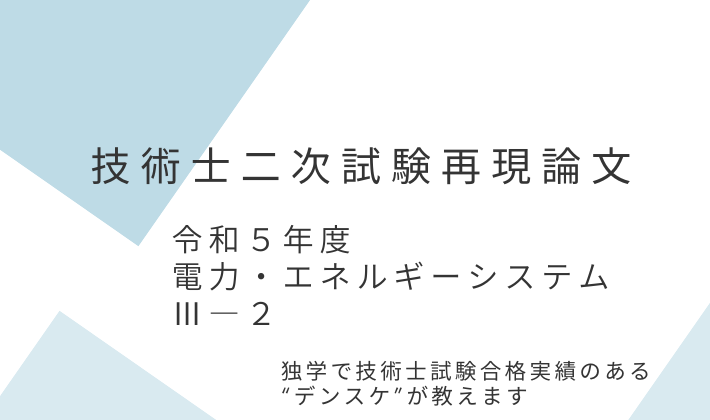こんにちわ、デンスケです!
令和6年度技術士第二次試験(電気電子部門)に独学で合格実績のある”デンスケ”が、”最新”の技術士試験の合格ノウハウを伝えたいと思います。
ブログに不慣れなので、まずは単純に、自分が試験で回答した論文の再現を公表してみます。拙い内容で、誤りも含まれると思いますが、ご容赦ください。
今回は、令和5年度 電力・エネルギーシステムⅢ―2です。
合否通知では、A判定(得点率60%以上)となっていました。
問題
2030年再エネ目標の達成や2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、再エネの大量導入を支えるための電力流通設備の増強が重要である。これを実現していくためには費用を可能な限り抑制する必要があり、既存系統の有効活用が不可欠となる。このような状況を踏まえて、電力・エネルギーシステム分野の技術者として、以下の問いに答えよ。
(1)既存系統における送電可能量拡大に関する課題を多面的な観点から抽出し、その内容を観点とともに3つ示せ。
(2)前問(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題の解決策を3つ示せ。
(3)前問(2)で示した解決策に伴って新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
再現論文
1.既存系統における送電可能量拡大に関する課題
(1)発電制約の観点
送電線や変圧器の電力流通設備は、複数系列を並列に運用しており、1系列が停止しても問題のないようにあらかじめ発電制約を設けている。電力設備を守るためには有効であっても、既設系統を有効活用としているとは言い難い。発電制約の観点から、発電制約を最小限にしていくことが、送電可能量の拡大に対する課題となる。
(2)機器耐量面の観点
送電線や変圧器は、外気温、風速、日射量等の周囲環境によって流すことのできる潮流が異なる。想定される最も過酷な前提条件をもとに算出した運用容量を採用することは、既存系統の有効活用には反している。
機器耐量面の観点から、刻々と変化する周囲環境に応じた運用容量を適用していくことが課題となる。(ダイナミックレーティング)
(3)潮流想定面の観点
電力流通設備の潮流を運用容量以下に収めるため、需要状況、再エネの発電状況など、過酷な条件を用いて潮流を想定することは、既存系統の有効活用の観点からは最適ではない。潮流想定面の観点から、合理的な潮流想定を行っていくことが課題となる。
2.発電制約の課題に対する解決策
送電可能量拡大に対して最も改善の余地があると想定される課題(1)を最重要課題と考える。解決策を以下に示す。
(1)N-1電制の活用
N-1故障が発生時に、瞬時に解列させ、残設備の運用容量以内となるように潮流を制限させる装置をN-1電制という。例えば、2回線送電線の場合、従来、運用容量が1回線容量に制限されていたが、N-1電制を適用することによって、平常時の運用容量を2回線容量まで拡大することが可能となる。また、N-1電制により解列する電源を新規参入者に限定せず、既連系者も考慮することにより、より効率的な運用が可能となる。
(2)ノンファームシステムの適用
実需給に近い断面で電力流通設備の潮流想定を行い、運用容量を超過する場合は自動で発電機の出力を抑制するシステムをノンファームシステムと言う。実需給に近い断面の潮流想定は精度が高いこと、部分抑制も可能としていることから、発電制約量を減少させる効果がある。
(3)再給電ルールの整備
系統の混雑が発生した場合、従来は先着優先の考え方に基づいて来たが、後着事業者に発電制約を設けることが必ずしも有効とは限らない。出力調整可能な火力機を優先的に抑制するなど、優先順位を見直すことによって正味の送電可能量を拡大することが可能となる。
3.新たに生じうるリスクと対策
(1)システム停止リスク
N-1電制やノンファームシステムを適用した場合、システム停止時に運用容量が不足したり、運用容量超過による設備損壊や公衆災害のリスクが生じる。対策として、システムの二重化やセキュリティ対策、自動点検・自動監視機能の実現があげられる。また、システム停止時に人間系で対応するための手順や連絡体制を整備することも重要である。
(2)短絡容量の増大
既存系統における送電可能量を拡大する方策を実施した場合、従来の系統制約では連携できなかった発電機が連系し、短絡容量が増大する可能性がある。短絡容量の増大は、短絡電流が遮断器の定格遮断電流を超過し、設備損壊や波及停電の発生リスクを生む。また、短絡電流の増大により、保護リレーが誤動作し、不要停電が発生するリスクもある。対策として、発電機の連系検討において、短絡容量をしっかりと検討し遮断器の定格遮断電流の問題がある場合は、遮断器の更新、源流リアクトルの設置、系統の分割などの対策をとる。保護リレーの問題の有無も確認し、問題がある場合は保護方式の変更やCT飽和対策などをとる。
以上