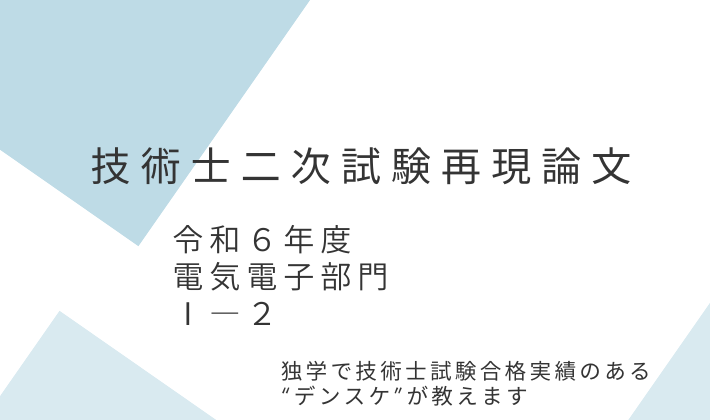こんにちわ、デンスケです!
令和6年度技術士第二次試験(電気電子部門)に独学で合格実績のある”デンスケ”が、”最新”の技術士試験の合格ノウハウを伝えたいと思います。
ブログに不慣れなので、まずは単純に、自分が試験で回答した論文の再現を公表してみます。拙い内容で、誤りも含まれると思いますが、ご容赦ください。
今回は、令和6年度 電気電子部門Ⅰ―2です。
合否通知では、A判定(得点率60%以上)となっていました。
問題
本問は、電気電子分野における技術の進展と普及の問題について問うものである。新しい技術(手法を含む)を取り入れる場合と、成熟した技術(いわゆる枯れた技術)を使い続ける場合とを比較して、どのような技術得失を判断して本業の技術の導入戦略に取り組むべきか、企業規模の大小の違いによる側面を踏まえてどのように本業を発展させていけばよいか、これらの解決策と将来像についての道筋を示すことが求められる。以下の設問に技術面で解答せよ。(人事、政策などは含まない。)
(1)電気電子分野の技術者としての立場で、技術の進展と普及について、下線部のキーワードに基づいて、多面的に異なる観点から3つの技術課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その技術課題の内容を説明せよ。(*)
(*)解答の際には必ず観点を述べてから技術課題を示せ。
(2)前問(1)で抽出した技術課題のうち最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、これを最も重要とした理由を述べよ。その技術課題に対する電気電子分野関連における解決策を3つ、新しい技術並びに成熟した技術の具体名とともに、専門技術用語を交えて示せ。
(3)前問(2)で示した解決策に関連して、新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項とそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
(4)前問(2)で示した解決策の実施において、技術者としての倫理、社会の持続可能性を踏まえて必要な要件を題意に即して述べよ。
再現論文
1.技術の進展と普及に関する課題
(1)技術得失評価手法の観点
新しい技術の方が成熟した技術に対して総合的なメリットがあれば、技術移行を進めるべきである。しかし、新しい技術導入時のイニシャルコストや労力、未知のリスクが発生する懸念などから現状維持バイアスが働き、技術移行が進みにくい傾向がある。このため、技術得失評価手法の確立が課題である。
(2)企業規模の観点
優れた技術は、速やかに取り入れた方が有効である。しかし、企業規模が大きくなるほど、失敗を恐れたり、全ての事業に適用しようとしたりすることで、技術移行が遅延する傾向が考えられる。このため、可能な限り細かい単位に区分し、スモールスタートさせる手法の確立が課題である。
(3)解決策と将来像についての道筋を示す観点
新しい技術は導入したらそこで終わりではなく、目指すべき将来像の実現に向けてPDCAサイクルを回していく必要がある。このため、将来像実現に向けての道筋を明確に示し、関係者で認識を合わせながら道筋を見直していくことが課題である。
2.最重要課題と解決策
新しい技術を取り入れるという判断なくしては技術の進展と普及は成り立たないことから、「技術得失評価手法の確立」が最も根本的な課題であり、重要である。また、当該課題解決により、スモールスタートやPDCAサイクルを円滑に回すことに対しても波及効果が期待できる。解決策を次に示す。
(1)AIを活用した発電計画策定
従来はベテラン社員の知識と経験をもとに発電計画を策定していたが、AIの機械学習を用い、気象条件や各種発電制約を考慮した発電計画の自動作成することに移行することが考えられる。これにより、発電計画策定時間や労力の削減、経済性の向上等が期待できる。イニシャルコスト、ランニングコストを考慮してもメリットを見いだせられれば、積極的に導入すべきである。ただし、AIの作成した発電計画が妥当であることを確認することにも留意が必要である。
(2)ドローン、IPカメラを用いた設備点検
従来は現地出向の上、設備点検を行っていたが、ドローンやIPカメラを用いて遠隔で点検を行うことに移行することが考えられる。移行にあたっては、カメラの解像度が十分であること、必要時に確実に運用できることを確認する必要がある。
(3)IEDリレーの適用
従来型の保護リレーは電気信号を用いたリレー装置から構成されているが、光通信を用いた演算装置からなるIEDリレーに移行することが考えられる。移行にあたっては、電気所の装置一式を移行したほうがコストや運用面でメリットがあることから、既存設備の経年状況についてよく考慮する必要がある。
3.解決策に関連して新たに生じる懸念事項と対策
技術得失評価手法の確立により、新しい技術の導入が進み、新しいシステムを構築した場合、システム停止時に電力の安定供給に支障が生じるリスクがある。対策として、ファイアウォールやセキュリティ対策に加え、システム二重化、ヒューマンエラー防止のための人材教育の徹底などでシステム停止を防止する。システムの停止がリスク許容度の範囲内であれば、システム停止時の運用ルールの整備や早期復旧体制の整備等で対応することも考慮する。
4.技術者倫理、社会持続可能性からの必要要件
技術者倫理については、公衆の福利を最優先に考える。各種システム構築にあたって、コストや納期を優先してしまい、計算書の改ざん等の不正が行われると、電力供給の停止や公衆災害発生のリスクが生じる。不正の防止のため、倫理教育の徹底に加え、不正の行えないシステム構築が有効である。
社会持続可能性については、環境負荷低減に留意する。各種システム構築時に、エネルギー効率が高い機器を選定することや、廃棄時にリサイクルしやすいケーブルを選定することは、環境負荷低減につながる。
以上