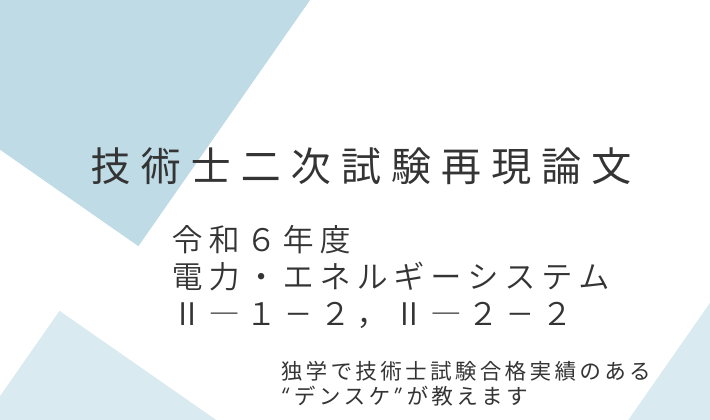こんにちわ、デンスケです!
令和6年度技術士第二次試験(電気電子部門)に独学で合格実績のある”デンスケ”が、”最新”の技術士試験の合格ノウハウを伝えたいと思います。
ブログに不慣れなので、まずは単純に、自分が試験で回答した論文の再現を公表してみます。拙い内容で、誤りも含まれると思いますが、ご容赦ください。
今回は、令和6年度 電力・エネルギーシステムⅡ―1-2,Ⅱ―2-2です。
合否通知では、A判定(得点率60%以上)となっていました。
Ⅱ―1-2 問題
架空送電線における雪によって発生する不具合を3つ挙げて、電力輸送面と設備被害面について発生要因と関連して説明し、防止対策について述べよ。
Ⅱ―1-2再現論文
1.架空送電線における雪によって発生する不具合
①着雪荷重による断線
湿って重たい雪が電線に着雪すると、雪の重みによって電線が断線するおそれがある。断線すると、電力供給が不可となる。
②ギャロッピング
湿った雪が電線に横から吹き付けると、飛行機の羽のように着雪する。風向きが逆になり、強く風が吹くと、よう力により電線が振動し、短絡事故にいたる恐れがある。短絡電流による熱で電線が溶断するおそれもある。
③スリートジャンプ
電線に着雪した雪が溶けて落ちるとき、電線が跳ね上がり短絡事故や断線にいたるおそれがある。
①~③に共通して、送電線の潮流が小さく、電線の放熱が小さいときに発生しやすい傾向がある。
2.対策
上記①~③共通の対策として、より線への着雪メカニズムから、難着雪リングとねじれ防止ダンパを送電線に取り付け、着雪を防止する方法があげられる。①については、着雪荷重を考慮した送電線、鉄塔の強度検討を行うことが挙げられる。③については、上線、中線、下線に水平オフセットを設け、電線が真上に跳ね上がっても短絡に至らない配置にすることが挙げられる。
以上
Ⅱ―2-2 問題
再生可能エネルギー電源の接続のために短期間でなるべく低廉な費用での系統連系が求められる例が多い。このような中で、送電線の増容量対策工事を進める場合、下記の内容について記述せよ。
(1)送電線の増容量に向けて、調査、検討すべき内容を説明せよ。
(2)業務を進める手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
(3)業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。
Ⅱ―2-2再現論文
1.送電線増容量工事の調査、検討内容
(1)送電線潮流の想定
過去の送電線潮流実績や将来の需要、発電動向をもとに、送電線潮流を想定する。潮流の向きは逆潮流、準潮流ともに想定し、厳しい条件を用いる。
(2)送電線スペック検討
送電線の想定潮流をもとに、線種等の検討を行う。別ルートでの送電線建替の他、既設ルートでの建替が考えられる。特に、一部区間だけの増強ですむ場合や鉄塔は建替えず線種のみの変更で済む場合は、コスト、工期麺で有利のため、積極的に既設設備を活用する。
(3)現地施工面
資材搬入経路、作業スペースを十分考慮の上、用地を確保する。近隣住民への影響が考えられる場合、影響低減策を検討の上、事前に理解を得るようにつとめる。既設設備の停止が必要かどうか検討し、必要な場合、系統運用者に停止可能な時期、期間について確認する。
2.業務手順と留意点・工夫点
(1)送電線仕様決定、資材発注、施工委託断面
前項の検討事項を考慮して送電線の仕様を決定する。資材発注、施工委託先の選定にあたっては、複数社に見積もりを取り、性能、コスト、安全性、環境適合性等を比較の上、総合的な判断を下す。
(2)現地施工断面
資材や現地施工のリードタイムを確認し、予め工程表を作成した上で進める。日々、進捗確認を行い、計画通りでない場合は、要因分析の上、工程の見直しを行う。工事完了時は検査体制を整備し、必要要件を満足していることを確認する。
(3)設備運用開始後
初期点検、定期設備点検を行い、不良が見つかった場合はリスク評価を行う。それに基づき、優先順位を定め、限られた予算、マンパワー等を配分し、設備保全を行う。
3.効率的、効果的に進めるための関係者調整方策
①系統運用者:工事に着手する前に、増容量後の送電線必要容量について確認する。打合せの議事録を共有することで認識を合わせ、後戻りのないように進める。
②規制担当官庁:送電線増容量工事にあたり必要となる手続き、リードタイムを確認の上、進める。
③資材メーカー、現地施工業者:リードタイムを確認の上、無理のない工程を立案する。工程表は関係者で共有し、認識を合わせながら進める。
④近隣住民:搬入経路や作業スペースの用地専有や工事車両の通行について事前周知し、十分な理解を得たうえで進める。工事期間中は、交通誘導員を配置するなど、近隣住民への影響を低減するように努める。
以上