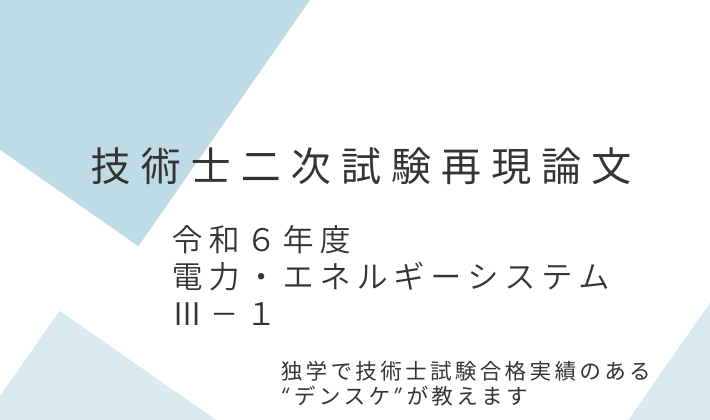こんにちわ、デンスケです!
令和6年度技術士第二次試験(電気電子部門)に独学で合格実績のある”デンスケ”が、”最新”の技術士試験の合格ノウハウを伝えたいと思います。
ブログに不慣れなので、まずは単純に、自分が試験で回答した論文の再現を公表してみます。拙い内容で、誤りも含まれると思いますが、ご容赦ください。
今回は、令和6年度 電力・エネルギーシステムⅢ―1です。
合否通知では、B判定(得点率40%以上60%未満)となっていました。科目ⅡとⅢの合計得点がA判定となり、運よく二次試験は合格できていました。
問題
太陽光発電や風力発電といった気象条件によって発電量が左右される再生可能エネルギーの有効活用のため、電力貯蔵技術への期待が高まっている。電力の安定供給を将来にわたり実現するべく、これらの技術の活用によるカーボンニュートラルの推進が求められている。このような状況を踏まえて、電力・エネルギーシステム分野の技術者として、政策面ではなく技術面から、以下の問いに答えよ。
(1)具体的な電力貯蔵技術を複数挙げて、それぞれについて多面的な観点から比較・評価し、電力貯蔵技術の導入・普及を進めていくうえでの課題を、観点とともに3つ示せ。
(2)前問(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題の解決策を3つ示せ。
(3)前問(2)で示した解決策に伴って新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
再現論文
1.電力貯蔵技術の導入・普及を進める上での課題
具体的な電力貯蔵技術と特徴について以下に示す。
①揚水発電:電力を使って下池から上池に水をくみあげ、逆向きに水を流したときに発電する。大規模な土木工事が必要となるため、開発可能な場所が限られる。
②蓄電池:充電と放電により電力貯蔵運用を行う。鉛蓄電池、リチウム電池、NAS電池、レドックスフロー電池等、様々なタイプが有り、家庭用の小型のものから蓄電所の大型のものまで普及してうる。
③水素:水の電気分解によって水素を製造することでエネルギーを貯蔵する。水素は燃料電池として用いるほか、メタンやアンモニアの生成や水素還元鉄への利用等様々な活用が考えられるが、技術は未成熟である。
電力貯蔵技術の導入・普及にあたっての課題について以下に示す。
(1)電力流通設備の熱容量の観点
立地制約から、再エネの発電設備と電力貯蔵設備は離れた場所に設置しなければならないことが考えられるが、間の電力流通設備の熱容量が普及の支障となることが考えられる。このため、電力流通設備の熱容量制約の解消が課題である。
(2)活用方法の観点
単に余剰電力を貯蔵するだけではなく、需給調整力としての活用や送電線混雑解消のための活用等、多様な活用方法を用意することで、普及が進むと考えられる。このため、各種活用システムの開発が課題である。
(3)水素として貯蔵したエネルギーの活用の観点
水素は他の電力貯蔵技術と異なり、非電化分野への活用ポテンシャルを秘めているが、活用技術が未成熟である。このため、水素の活用、輸送技術を発展させていくことが課題である。
2.最重要課題と解決策
「電力流通設備の熱容量制約の解消」は各電力貯蔵技術に共通する課題であり、導入効果に大きく影響するため、最重要課題と考える。当該課題解決により導入効果を拡大することで、他の課題にも波及効果があると考えられる。解決策を次に示す。
(1)電力貯蔵設備の適地への誘導
電力流通設備の増強を行うよりも、増強が不要な場所で系統連系するよう電力貯蔵設備の設置場所を誘導したほうが、コスト、工期、環境負荷低減面等でメリットがある。また、送電ロスの低減も期待できる。一般送配電事業者には、適切な情報開示が求められる。
(2)需要側ノンファーム型接続
発電側では、系統混雑時に発電を抑制することを条件に、設備増強なしで系統連系するノンファーム型接続が認められている。電力貯蔵設備では、需要側の送電線潮流で系統混雑が発生する可能性があるが、需要側にもノンファーム型接続を適用し、設備増強なしで系統連系を認めるのが合理的と考える。
(3)需要側N-1電制
通常、2回線送電線では、1回線停止になっても熱容量超過が発生しないよう、運用容量を1回線分の熱容量に制限している。N-1電制装置により1回線送電線停止時に即座に電源を制限することで、運用容量を拡大する取り組みが行われている。電力貯蔵設備の導入にあたって、需要側のN-1電制装置を開発することにより運用容量を拡大することが有効である。
3.解決策に伴って新たに生じうるリスクと対策
ノンファームシステムやN-1電制装置を適用した場合、システム停止時に熱容量超過が発生し、設備損壊や公衆災害発生などのリスクが生じる。対策として、ファイアウォールやセキュリティ対策等に加え、システム二重化、ユーマンエラー防止のための人材教育の徹底などによりシステム停止を防止する。また、システムが停止してしまった場合の暫定運用方法の整備や早期復旧のための体制整備も有効である。
この他のリスクとして、蓄電池や燃料電池等の回転機以外の系統連系量が増えると、慣性力の低下により、系統事故時のRoCoFが増大し、PCS電源の一斉脱落等が生じるリスクがある。対策として、PCSへ模擬慣性力の導入や同期調相機、系統安定化装置の導入があげられる。
以上
所管
上記の再現論文は、残念ながらB判定でした。
そもそも再現精度が高くなく、明確な原因分析は難しいですが、反省点を記載しておこうと思います。
解決策(1)電力貯蔵設備の適地への誘導は、「政策面ではなく技術面から」という問題の指示にマッチしていなかったかもしれないと思っています。「多面的な観点」を意識しつつ題意にそうというのは難しいです。前年度にも同じ失敗をしているのにもかかわらず、同じ後悔をしてしまうというのは、本番の焦る気持ちの中で冷静な判断をすることの難しさなんだと感じています。こういった内容に触れる場合は、技術面であることをアピールするため、「情報開示システムの開発」等、なんでもシステム化してしまえばいいのではないかと思っていましたが、本番でそこまで書けませんでした。。。
また、解決策(2)需要側ノンファーム型接続、(3)需要側N-1電制 についても、採点者の方に意図をうまく伝えられなかった可能性があると考えています。デンスケとしては、蓄電池の充電を抑制するイメージでしたが、文面上、需要家の電気使用量を抑制するように解釈されてしまったのかと。。。
反省するときりがないですね。令和6年度の再現論文は以上です。拙い内容ですが、読んでいただいた皆様に少しでもお役に立てれば幸いです。